| 1月19日は甲斐直心館では朝稽古を行いましたが、午後6時からは敷島総合体育館で甲斐支部合同稽古会が行われました。館生の中には中学校の部活動もあったため、この日は3部練という強者もいました。一日2回、3回の稽古に明確な目標を持って同じような気持ちで臨めれば着実に上達していくと思います。
先日、脳科学者の茂木先生のテレビ番組で「アウェー体験が自己を大きく向上させてくれる」ことを取り上げていました。出稽古で大幅な上達をすることがあるのはこういうことなのだなあと納得しました。いつもの稽古場所と違うところで行われる合同稽古会も同じような効果が期待できるはずです。
この日は高校生が冬季大会だったため、日本航空高校、農林高校生も稽古参加はなく、参加者は総勢50人ほどといつもに比べて少ないものでした。1時間半の稽古の中で、2月10日の本部審査に向けた確認の意味で、日本剣道形、基本技稽古法も取り入れることにしました。
敷島の小林君に号令を掛けてもらいました。大きなはっきりとした号令で素晴らしいものでした。正座後、相川支部長先生から親に感謝することなど多岐にわたる剣道講話がありました。支部稽古会は本年度7回目で、毎回の相川先生の講話をまとめると素晴らしい講話集が出来上がると感じます。
小林君の号令で準備体操、素振りを行い、ただちに日本剣道形、基本技稽古法、初心者錬成に分かれて稽古を25分間行いました。
日本剣道形を実践した中には木刀を持っていない中学生もおり、竹刀では感覚をつかめないこともあるためいささか残念でした。甲斐直心館の館生は稽古時には常時、竹刀と木刀を持参するよう促しています。全体に、直心館の館生を含め、日本剣道形の細かいところが曖昧にされている印象を受けました。自分で分からないところは先生方に質問して、明確なものにする必要があります。不断の修錬をしていってほしいと感じました。
面着け後からは40分しかありませんでした。25分間を切り返し、打ち込み稽古に充て、最後の15分間を互格稽古の時間としました。
昨年剣道七段に合格した敷島の横山先生にも初参加していただきました。神宮寺先生も稽古をつけていただいたようです。間もなく65歳とのことですが、鋭く、冴えた打ちは勉強になります。
終わりの正座の理事長講評では「もっと大きな声を出してほしい」とお願いしました。有効打突の条件は「充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるもの」とされています。最初に「充実した気勢」とあることを忘れないでほしいと思います。
2月10日の本部審査会の申し込みは甲斐支部全体で五十数人に上るそうです。2月期としては多めです。そのうち甲斐直心館関係は18人ですので、約3分の1を占めています。中学校の女性教員で部活動の顧問をしてから剣道を始め、今回二段を受審する先生が合同稽古に参加しました。その動きから、よく稽古していることが分かります。師弟同行の精神に頭が下がります。
次回、本年度8回目となる支部合同稽古会は本部審査前日の2月9日(土)13時30分集合、14時開始で竜王北中学校体育館で行われます。甲斐支部全体の剣道がますます盛り上がるよう願っています。次回の合同稽古会でも日本剣道形を行いますので、参加者は木刀も用意してください。  にほんブログ村 にほんブログ村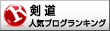  |
|