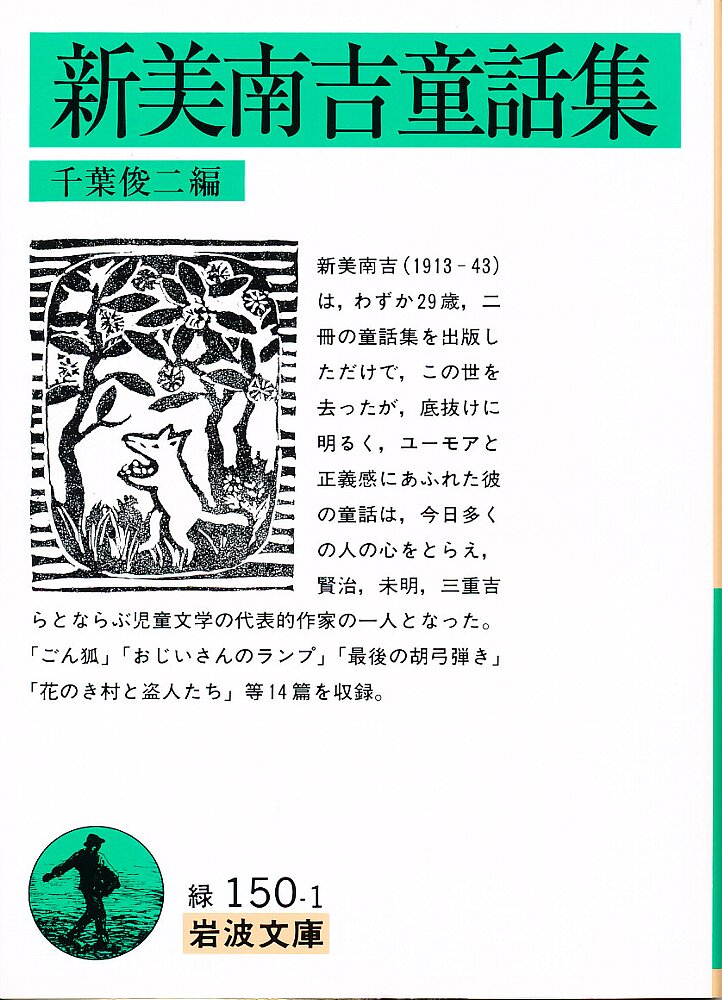『新美南吉童話集』のなかでも「最後の胡弓弾き」という作品がとりわけ好きだ。これは〈童話〉の域を超えて優れた作品だと思う。
木之助は小さい時から胡弓の音が好きだった。十二になって上手な牛飼いのところへ通って習い始め、旧正月になると従兄の松次郎と町へ門附に出かけた。太夫の松次郎が着物、袴、烏帽子で鼓、木之助はよそ行きの晴着にやはり袴で胡弓を持っていた。町には二人を可愛がってくれる味噌屋もあった。小さな村には何組かいて、上手な者は都会や信州へも行って稼いだ。
門附は次第に流行らなくなり、呑んだくれた松次郎は「もう止める」と言い出す。迷った挙句、木之助は一人で出かける。味噌屋の主は彼を歓迎してくれる。
木之助が病気をして二年間を置いて出かけろと、町の家には「諸芸人、物貰い、押し売り、強請(ゆすり)、一切おことわり、警察電話一五〇番」と張り紙がしてある。味噌屋では意地悪だった女中が中へ入れてくれるが、主は亡くなっていた。仏前で弾いて門を出る。
古物屋の前で、木之助は胡弓を売り払おうとする衝動に駆られる。30銭だった。末っ子のためのクレヨンを15銭で買うと、胡弓のことがしきりに悔やまれた。買い戻そうとすると今度は60銭だった。
「午後の三時頃だった。また空は曇り、町は冷えて来た。足の先の凍えが急に身に沁みた。木之助は右も左もみず、深くかがみこんで歩いていった」
何度も読んでいるが、私はこの童話の胡弓の音を「越中おわら風の盆」の闇夜で聴いたりした、どちらかと言えば哀切な音として聴いていたのである。さもなければ、牛飼いに5,6曲習ったというし、味噌屋の主が好んで鑑賞してくれたというから、芸術音楽としてのたとえば藤枝流の「鶴の巣籠」とか「蟬の曲」「千鳥の曲」『栄獅子」「下り葉」「唐子楽」といった雅なもののようにも受け取っていた。
ところが、「日本の放浪芸」というCDで、鼓、三味線と共に正月に門附をして歩く尾張万歳、三曲万歳を聴いてはっとした。これは「ちゃかぽん、ちゃかぽん、ぎーこ、ぎーこ、ぺん、ぺん」と至って陽気で賑やかなのである。元来、正月の祝福芸なのだからそうあるべきなのが本当で、聴きすすむと、鳥取の人形芝居の大黒舞も(三味線、胡弓、太鼓)、香川のはりこま(三味線と胡弓)も同じく、実に聴いているこちらの頬が緩むような、いかにもおめでたい芸だった。
私は分からなくなってしまった。25歳の作者が書いたこの童話のBGMを賑やか、それとも哀切、どちらに聴こうか、と。それとも、音曲が底抜けに明るいから、余計に状況が切なく感じられるのだろうか、とも。