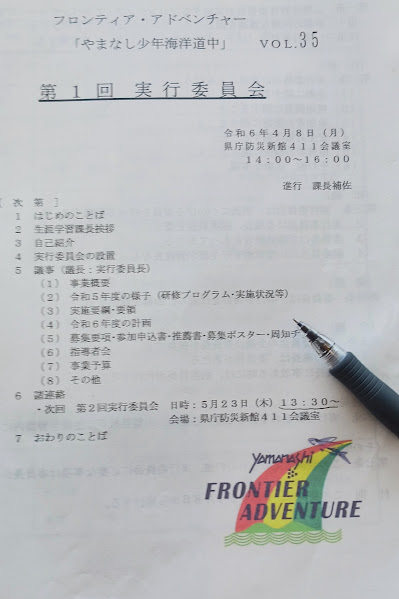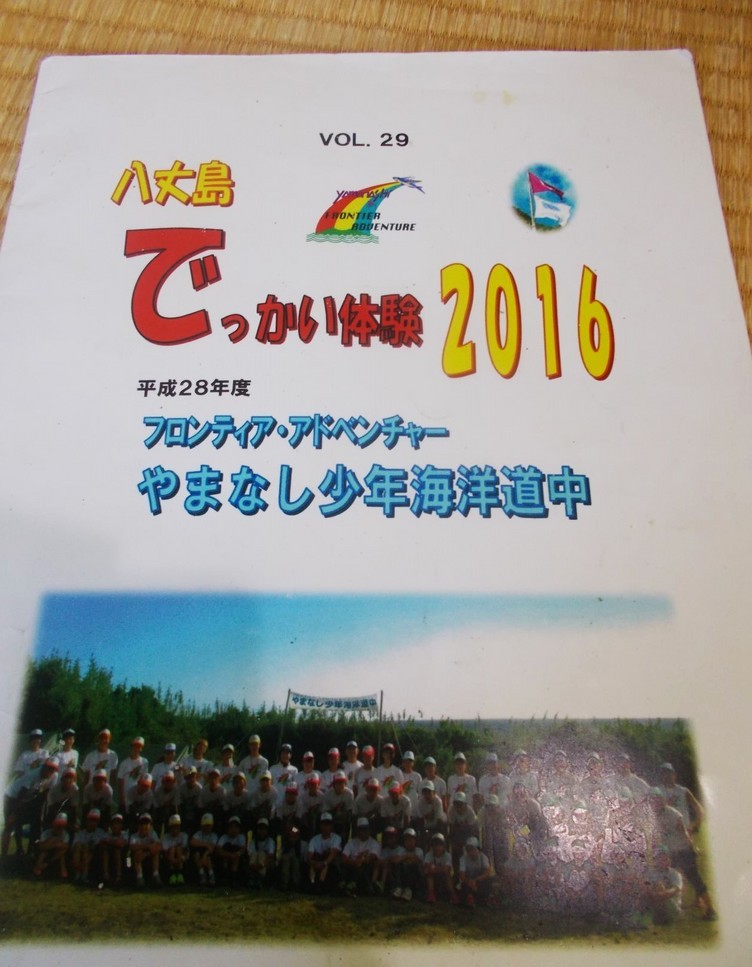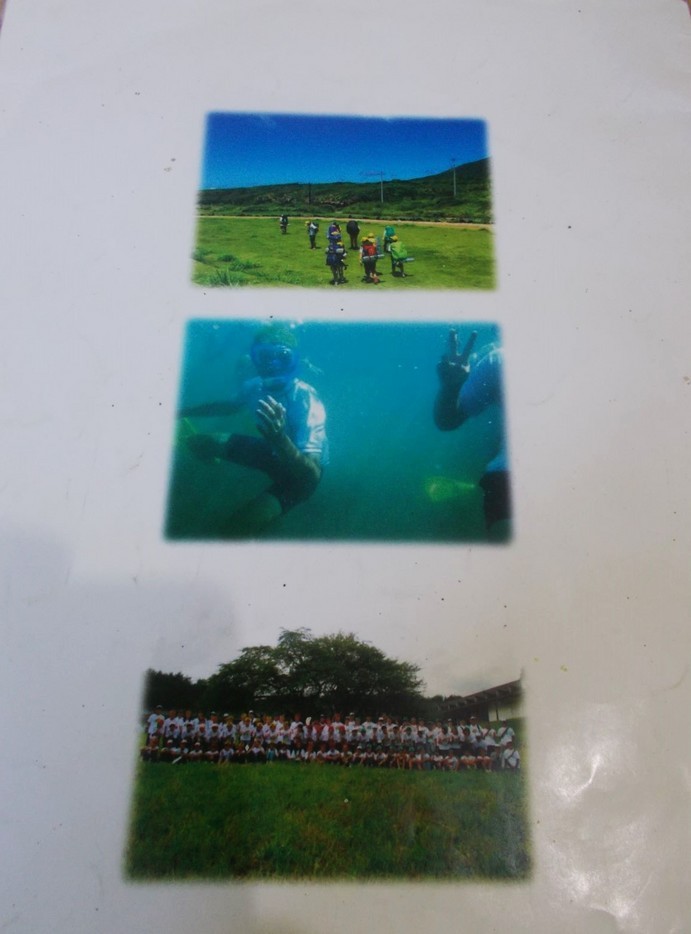皆様、おはようございます。
いやあ、すっかり春ですね~

桜

が咲いて、鳥

が鳴いて、
4月の中旬まで、桜がもってるのも、
ねえ、久しぶりですよ

ところで、
ついに、今年も始まりましたぁ!!
何が?って、
決まってるじゃあ、ありませんか

八丈島での長期自然体験事業、
『やまなし少年海洋道中2024』が、
いよいよ始まりました。
去る4月8日の月曜日―
第一回の、実行委員会が開催されました。
その席で、今年度の事業計画(案)が示され、
各地域の募集を担って戴く、実行委員の皆様に、
事業の告知と、参加者募集と取りまとめまでの、
スケジュールを共有致しました。
コロナ禍による2年間の中止を経て、
今年は、35周年のメモリアルイヤーとなります

一方、物価高騰の波は、
ますます高く押し寄せて来ていて、
無事な遂行に向けては、様々な工夫も必要となります。
ご家庭にとっても、ご負担を賜る事にはなるでしょう。
ですがっ、
その波にぶつかっても尚、
このキャンプに参加する事で、
中学生達は、絶対に大きな成長を遂げるでしょう。
ご安心下さい。
八丈島の多くの人達が、
山梨の中学生がやって来る夏

を、
本当に、心待ちにしてくれています。
指導者も、全力で体験をサポート致します。
どうぞ安心して、ご参加戴きたいと思います。
この記事がUPされる週のどこかで、
お子様が、学校からチラシと募集要項を、
持って帰って来る事でしょう。
お子様が、「コレ、行きたい・・・」
って、保護者の皆様に伝えて来たら、
「頑張っておいで・・・」
と、是非とも背中を、押してあげて下さい。
中学生達を引っ張る大学生のリーダー達も、
順調に選考が進んで居ります。
今年の夏、
でっかい体験、一緒にするじゃんけ