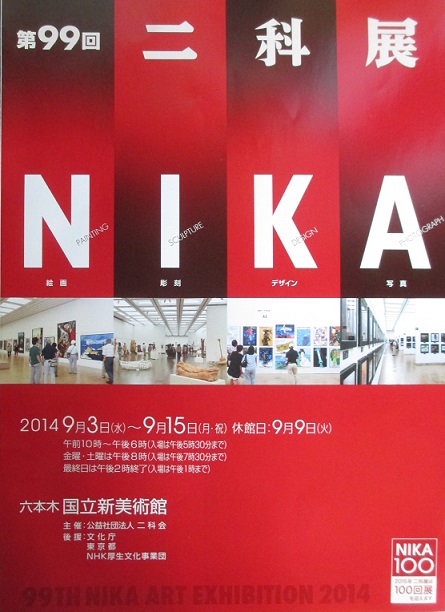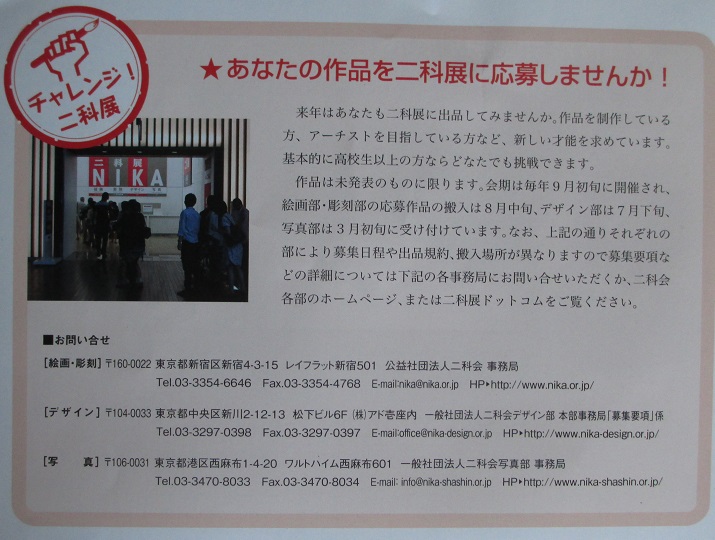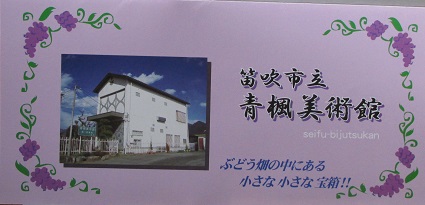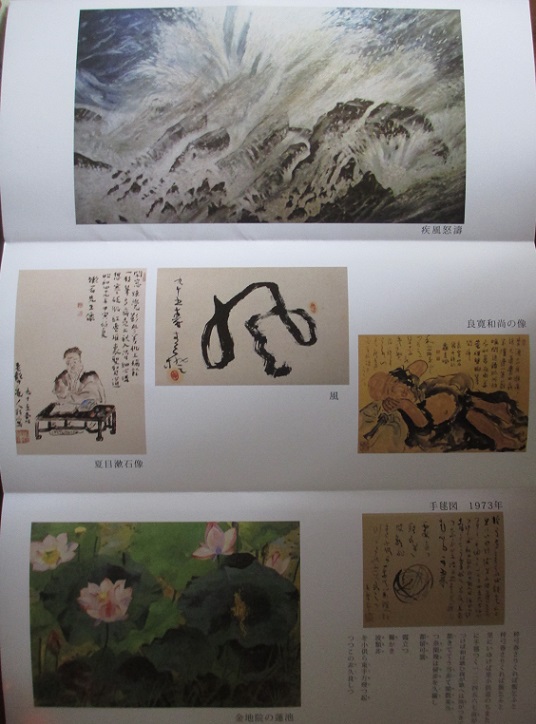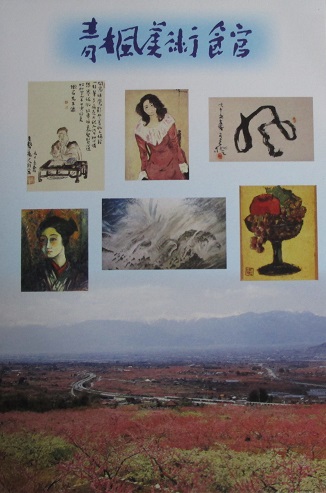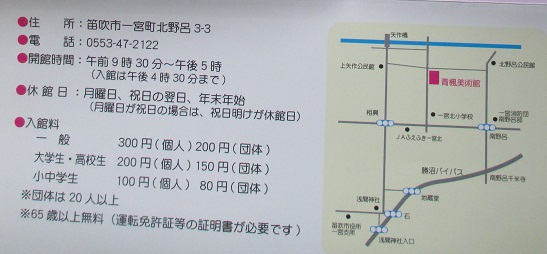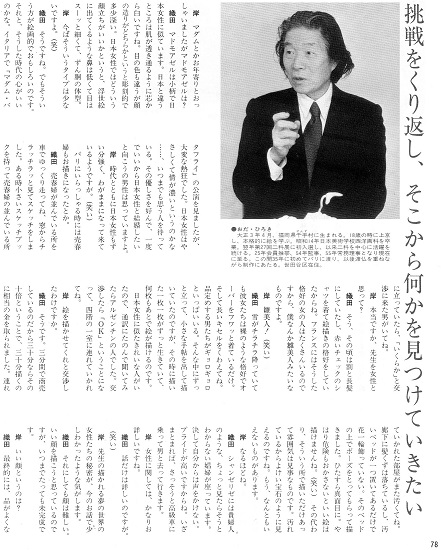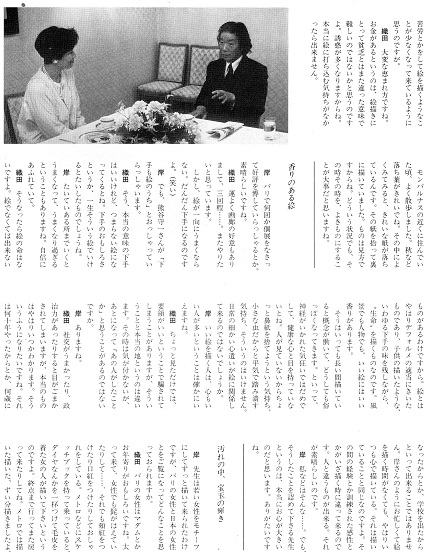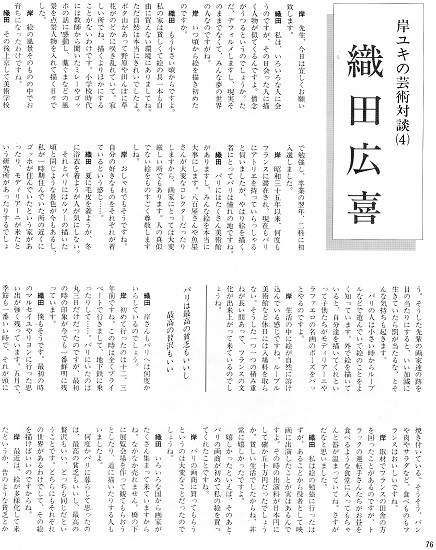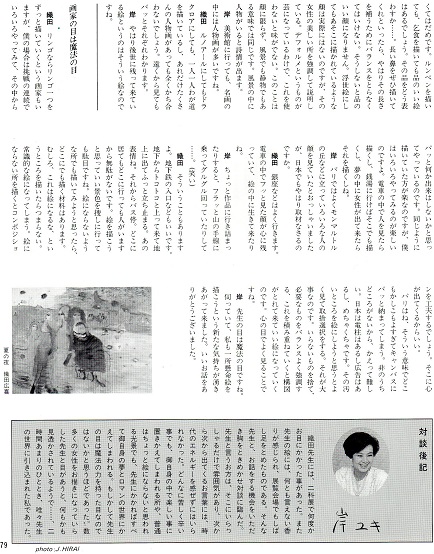�m���Ă܂����R���̕�A�����p��
�@��ȎR���x���́A�������p�قł̑�l��x���W��
�I�����܂������A���̉�����ɓJ���s�������p�يW
�҂��������ŗ��ꂳ��A��ȎR���x���̊��������
�����A�����p�ق̑��݂��ȊW�҂ɓ`���Ăق�����
�̃��b�Z�[�W���܂����B
�@�Q�O�O�T�N�ɎR�����k�m�s�ɈڏZ���A�x���ݗ��ɒ��́A
���Ƃ����̎R�����ɓ�ȉ�̊����̎�܂��Ǝv���Ċ���
���A�x�����߂鎄�͐����p�ق̂��Ƃ͑S���m
�炸�ɂ��܂����B
�@���v�Вc�@�l��ȉ�͍��N�ݗ��S���N���}���A���N
�͑�S��L�O�W��\�肵�Ă��܂����A�����p�ق̑���
��m�������Ƃɕs�v�c�ȏ��荇�킹�E���������Ă��܂��B
�@�Ƃ����̂������p�ق́A�P�O�O�N�O�̓�ȉ�n�ݎ҂�
��l�Óc���̔��p�قȂ̂ł��B�Ȃ����s�o�g�̐�
�̔��p�ق��R�����J���s�ɂ���̂������ÁX�A�x���W
�I����A���������p�ق�K�₵�A�����܂����B
�@�Óc���Ɛe���̂�������{���o�g�̗��j�Ə��r�B��
�����A�R�����̕����̌���ׁ̈A���p�ق���肽���Ƃ���
�v����Óc���ɓ`�����Ƃ���A�����S�ł���A���p��
�ݗ��̎������ɖ𗧂ĂĂق����Ǝ����̍�i���\�_��
��t�����B���r���͒Óc���̍�i�邱�ƂȂ��A�X��
���̍�i�����W�A�����̃R���N�^�[�Ȃǂ̋��́E��
�d�Ȃ�A�W�܂������ɂ܂����p�i�͂T�O�O�_�B�R��
�������p�يJ�قɐ�삯�āA���r���͂S�O�N�O�Ɏ�����
������Ŕ��p�ق����āA�Óc���̍�i��W�҂̍�
�i�̌��J���J�n�������Ƃ����������A��ϊ������܂����B
�K�͂͂Ƃ������A�R�����ōŏ��̖{�i�I�Ȕ��p�قƌ�����
�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@���̌㏬�r���̂��⑰�����p�فE��i��J���s��
���A���݂Ɏ����Ă��邪�A�J���s�݂̂Ȃ炸�A
�R�����ɂ͋M�d�ȕ��������Ɗ����܂����B
�@�Óc���́A��Ȑݗ��҂̈�l�Ƃ��Ēm���邪�A
���̔g������̌o������A��ʂ̕��ɂ͓���݂̔���
�ʂ����邪�A�Ėڟ��Ɛe�����A���̏����̕\���G�Ȃ�
�������肪���A���̐l�^�Ӗ쏻�q�Ƃ̌𗬂��m����
����B
�@��ƂƂ��ėm��E���{��E���n��ɒʂ��A���ƁA�̐l�A
���M�ƂƂ��āA���NJ������Ɠ��}���`�|�p�ƂƂ��Ċ���
�����B�ŏ��̍Ȃ͗m��ƎR�e�q�q�ŁA��Ƀf�U�C�i�[��
���Ċ���A�R�e�m���w�@��n�݂������Œm����B
�@���A���h���}�u�Ԏq�ƃA���v�ŎR�������ڂ���Ă���
�����Ԏq�Ƃ̌𗬂⑺���Ԏq�̐��U�̗F�Ƃ��ēo�ꂷ��
�������@�Ƃ̌𗬓��A���̐����p�ق�K�˂�ƁA��
�̍�i�A�ނ̐����l��ʂ��đ����̃h���}�E�������y����
��Ǝv���܂��B�@�@
�@�����ĉ������A���������悯��Ƃ��������̒��A
����𓊂��A�����A�S���̈��D�Ƃɔ��p�ق��c����
���r���̑��ՁA���S�����M���v���ɋ�����l�X�A
���ꂱ���傫�ȃh���}�ł���A���r�������B�Ɏc����
�ő�̃��b�Z�[�W�ł͂Ȃ��ł��傤���B
���v�Вc�@�l��ȉ�i�G��E�����j�̓�ȎR���x��
�́A�R�������ł͂قڃ[������X�^�[�g�A�����̐l�̎x��
�āA��ȕS��L�O�W�̗��N�͎x���W��܉�̐ߖ�
���}���܂��B�x���Ƃ��ď\���߂��Ȃ������l�B�ƁA��
���p�يW�҂Ƌ��͂��āA�Óc���A���r�B������
���ՁE���т������A�S���ɍL�����M�������Ǝv����
���܂��B�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ȉ�R���x�����@�@��쌓�O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@