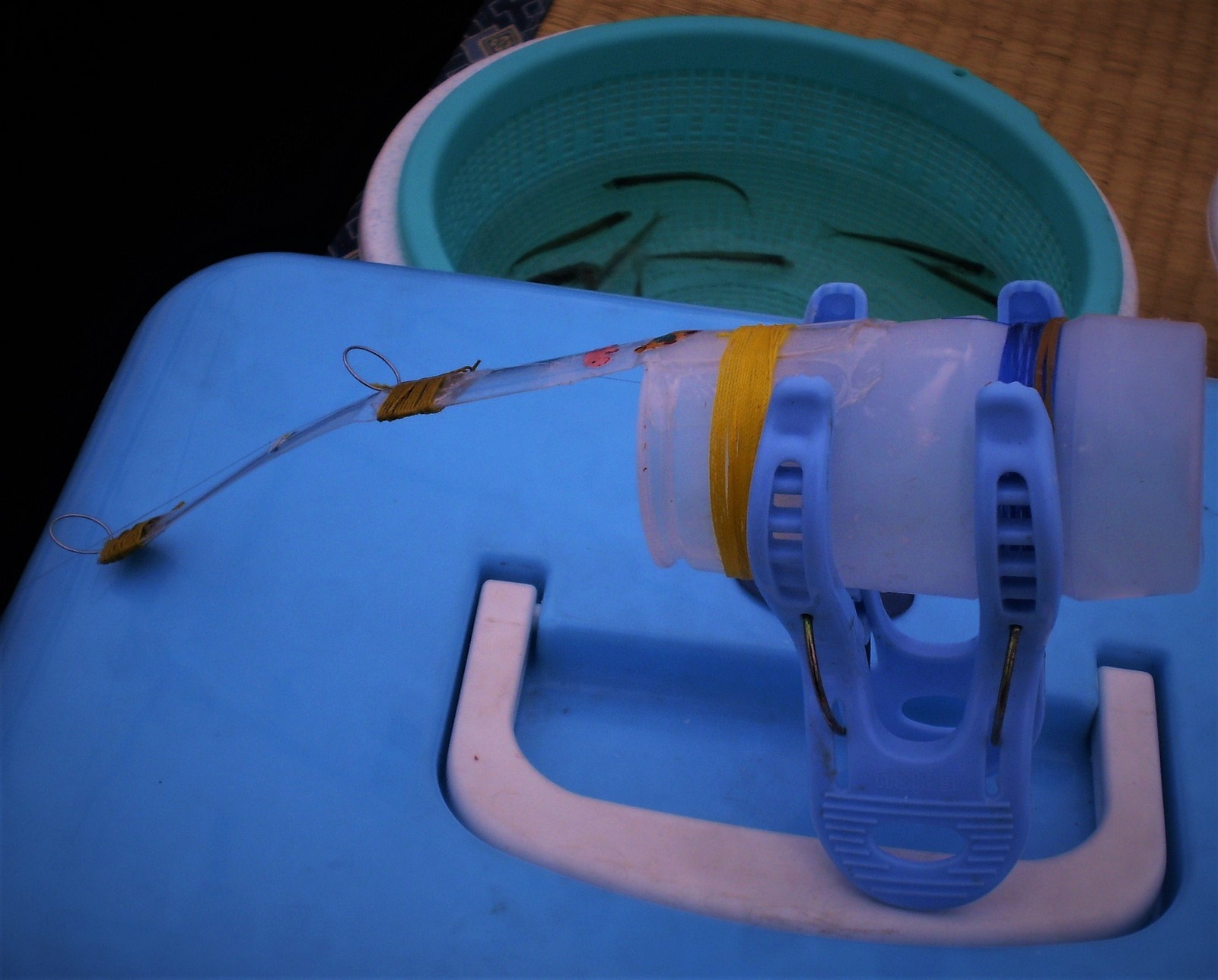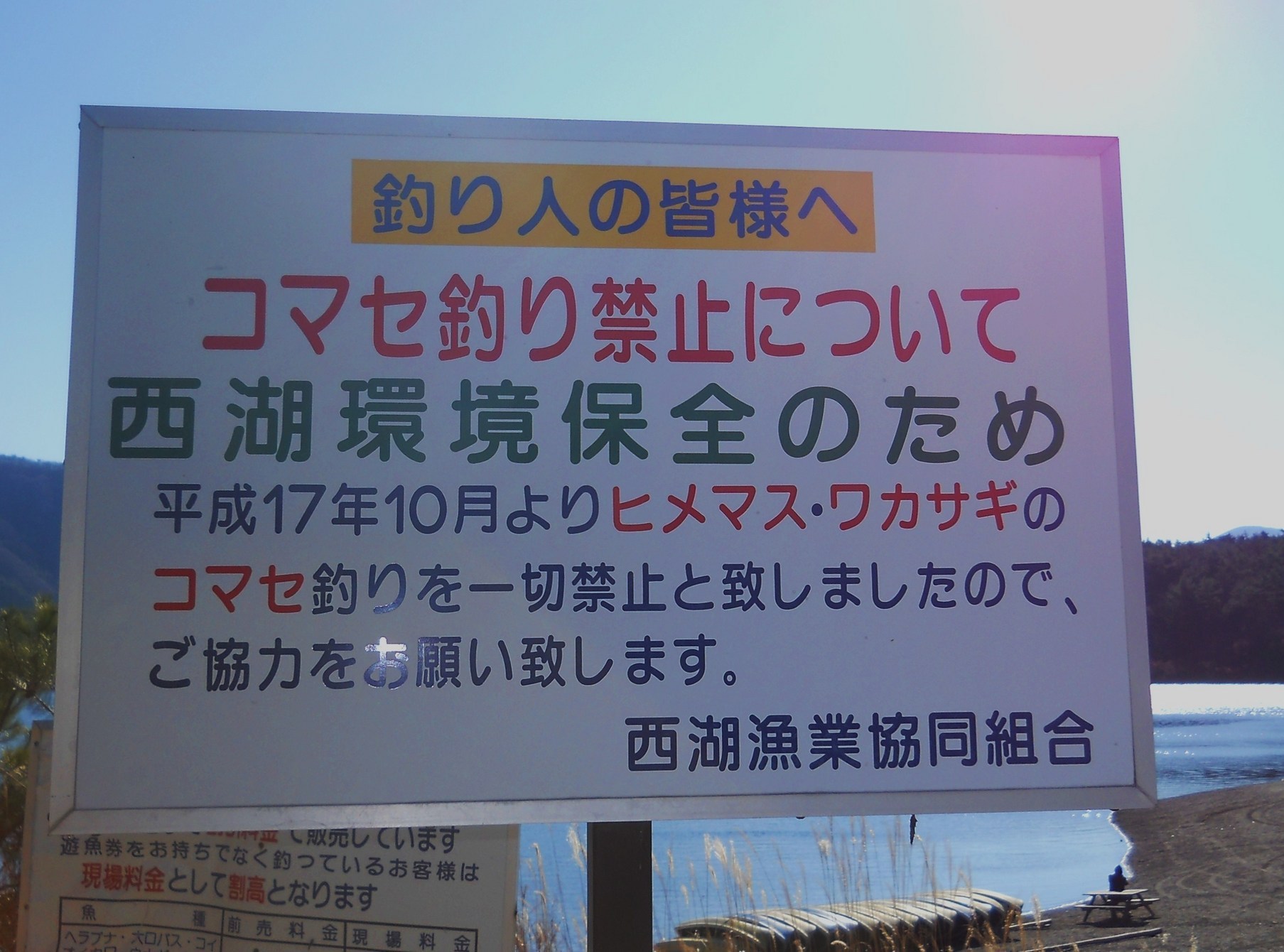���O2��̓��e�ŁA
���ꂩ��{�Ԃ��}���郏�J�T�M�ނ�́A
�ނ邾���ł͂Ȃ��y���ݕ���A
�l�C�̃h�[���D�ł̊����h�~��ɂ��Ă��b���܂����B
3��ڂ̍����́A
�^�[�Q�b�g�ƂȂ�w���J�T�M�x�ɁA���Ă��A
�������m���������đՂ����Ɖ]�����e�ł��B
���ĊF����A���J�T�M�͊����ŕ\�L����ƁA
�w�����x�ƁA�\�L���܂��B
���͐��Ɂu�����₯�́\�v�ƁA�]���Ӗ��ł����A
���̌��̎����ǂ����ď[�Ă��̂ł��傤�B
�悸�͂�������A�G��Ă��������Ǝv���܂��B
���͂��̌��́A�̂̈̐l�̎����A�u�������v���āA
�������肵�܂���ˁB���c�M�����Ƃ��A
�D�c�M�����Ƃ��A����ƍN���Ƃ��E�E�E�B
�܂����̏��R�̂��Ƃ��A�w�����l�x�ƁA�Ăт܂��B
������������ł��ˁB���J�T�M�́w���x�̎��́A
���́w���x�̎��ł��B
�]�˖��{11�㏫�R�A����ƐČ��ɑ��A
�헤���i���݂̈�錧�j�̖����˂������Y�̃��J�T�M���A
�N�v�Ƃ��Č��サ�����ƂɗR�����Ă��܂��B
�w���V��p���x�i���{�Ɍ��シ�邽�߂̋��j�ƁA�]�����ŁA
���̏�Ɖ�������āA�u�����v�ƁA����܂����B
���݂ł́A�_�ސ쌧�̈��m�ŁA
���̔N�̍ŏ��ɕ߂ꂽ���J�T�M���c���Ɍ��サ�Ă��܂��B
����Ȃɏ����ȋ��ł����A
���シ��قǔ����ł���Ɖ]���ł��傤�ˁB
���J�T�M�̊����\�L�̗R���ɑ����ẮA
����Ƃ��Ă̒m�������b�����܂��B
���J�T�M�́A�L���E���E�I�Ȃ̋��ł��B
�V�N�ȃ��J�T�M�́A���X�����L���[���̗l�ȁA
�u�₩�ȍ��肪���܂��B
�H���́A�����V��~�W���R�Ȃǂ́A
�v�����N�g������H�ŁA�ȑO�A�T�����ł��G�ꂽ�ʂ�A
�v�����N�g����ߐH���Ղ��悤�ɁA
�T�����قǂł͂Ȃ��ɂ���A��≺�{�̕��������ł��B
�����͂��悻1�N�B
���̗l�ɁA��N�ňꐶ���I���鋛����A�u�N���v�ƌĂсA
�A����A�n�[�Ȃǂ��N���̈���ł��B
�̒��́A�ő��15�a�قǂɂȂ�ꍇ������܂����A
�����悻10�a���炢�������̑傫���ł��B
�傫�Ȍ̂́A�~�C�^��DNA�������Ă���ꍇ�������A
�t�Ɉꐶ��W����ŏI���闤���^�̌̂́A
10�a���炢�̌̂������l�ł��B
����J�T�M�́A�S���e�n�̌Ώ��ɕ�������A
�~���̋M�d�Ȋό������ɂ��Ȃ��Ă��āA
�O�̓��e�ŏ������h�[���D�Ȃǂ́A
�ނ�D�Ɖ]�����A
�ό��D�Ƒ�����������������������܂���B
�ݗ���ł���Ȃ�����A
���̗l�ɖ{���̐����n�Ƃ́A
�傫���قȂ�ꏊ�ɈڐA�����A
�w�����ړ���x�x�Ɖ]���A����ΊO����Ɖ]�����ł��B
���A���J�T�M�̂悤�ɁA�ό������E�H�����Ƃ��ẮA
�t�����l���F�߂���A�ǂ��ɋ��Ă��A
�O����Ƃ��đ��O�Ȉ���������Ȃ��B���Ȃ��B
�ƁA�]���̂́A�������Ȃ��̂��ƁA�l�I�͎v���܂��B
�R���i�Ђ̃��J�T�M�ނ�V�[�Y���́A
�l�X�Ȏ����l���Ȃ���A�y����ł݂�Ɨǂ��Ǝv���܂��B
|