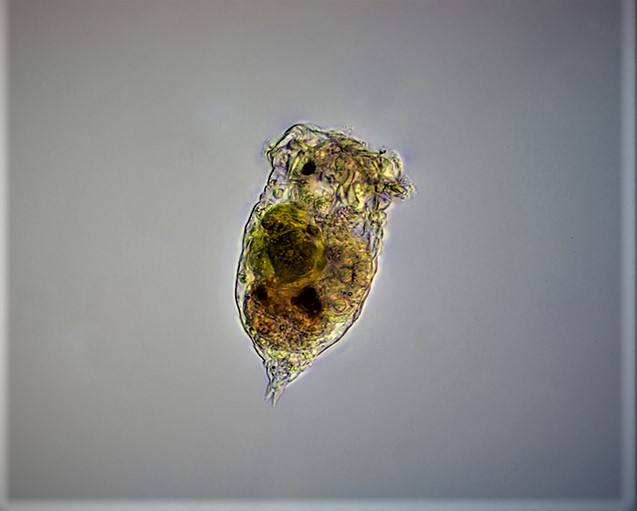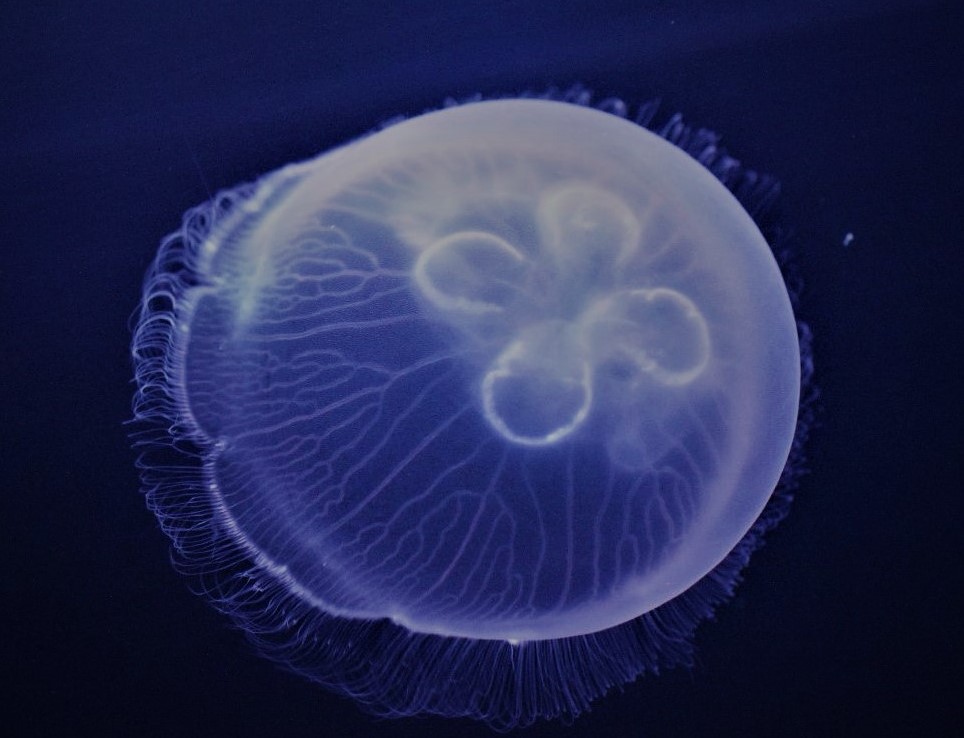�����́A
�u�H���̓��\�v���ފ݂̌䒆���ł��B
���ꂩ��A����Q��ɍs���ĎQ��܂��B
���˂Ă���A
���ފ݂ɂ͒ނ�����Ȃ��錾�\
���A���ċ���܂��̂ŁA
�����́A�ق��Ƃł���b��ł����܂��傤�B
�ނ�ɍs�������ɁA
����A�R�}�Z�̏L���𗎂Ƃ��āA
����ł����ς肵�����Ȃ��E�E�E

���āA�v�������Ă���܂���ˁB
�����ŁA����ȓ��e�ɂ��悤�I�I
���āA�v���t���܂����B
�F����A���^�N�V����D���ȓ��Ɖ]���E�E�E�H
�����ł��I�I
�ĎO�o�ꂵ�Ă���A�ɓ������̂��̓��ł�
 ���䓇��
���䓇���A
�ނ�Ɖ���Ƃ��Z�b�g�Ŋy���߂�ꏊ���A
�����́A�h�[���ƏЉ�悤�Ǝv���܂��B
�����œ���鉷�������܂�����A
�������䓇�ɒނ�i�ܘ_�ό��ł��j�ɍs���ꂽ�ۂɂ́A
����A������Ă݂ĉ������l

�h����̓����C���A���R�ǂ��̂ł����A
�������Љ���đՂ�����́A
�{���ɁA�ǂ������킢�[�����āA�C�����悭���āA
�ނ�̃|�C���g�ɂ��߂��̂ŁA��I�X�X���ł�

���āA��̎ʐ^�͉��x���Љ���đՂ��ċ���A
�R���̒��w���B�Ƃ̔��䓇�ł̃L�����v�ŁA
�w�T�o�C�o�����j�x�ƁA�]���v���O�����̂P�R�}�\
�q�ǂ��B�́A���������{�Ƃ��ĂP���Q���ŁA
�r�o�[�N�i��h�j���Ȃ�������̂ł����A
�������đՂ������̂́A
�q�ǂ��B�ł͂Ȃ����āA���Ɍ����Ă�Ŕł�
���ď����Ă���܂��H
�w�������ꉷ��x���āA�����Ă���܂��ł���I�H
���́A���̊Ŕ������Ă�ꏊ�̉��ɁA
�K�i���t���Ă��ł��B
�C�����E�E�E
�ŁA�~�肽��ɉ������邩���Ă����ƁA
���̒ʂ�A�������ł���

�������A�����I�I�@�^�_�ł���`

�A�������Ȃ̂ŁA
�����K���̉���ł��B
���̉���̊Ŕ̐�́A�C�Ɍ��������\
���Ȃ�ɍX�ɉ����čs���ƁA
�r���A���葤�ɂP���A����{�݂�����܂��B
�w�s�g�d�E�a�n�n�m�i�U�E�u�[���j�x�Ɖ]���܂��B
�u���[�|�[�g�E�X�p�@�U�EBOON (town.hachijo.tokyo.jp)���c�̎{�݂ł��B�����́A�L���ł��B
�ł��A�L�����ĊJ�����������āA
������������ł����B
���_���Ȍ����ŁA���ԏ�ɂ̓r���E���q�B
�썑���[�h�����ς��̊O�ςł��B
�����L�����āA�T�E�i�������ł��I�I
�����܂���

�܂��A���ꂾ�����Ⴀ����܂���B
�������ɁA�X�ɂ����P������{�݂�����܂��B
�u�₷�炬�̓��v�ł��B
������܂�Ƃ��������C�ł����A����ɂ����āA
�����C�̑�����A�����m���]�߂܂��B
�S����A���炰�鉷��ȂȂ��E�E�E
���Ȃ݂ɁA�������L���ł��B
�₷�炬�̓� (town.hachijo.tokyo.jp)�ł��A�܂��R���ŏI��肶�Ⴀ��܂���B
�X�ɉ���ƊJ�����ꏊ�������āA
�ቺ�ɕɂ�X�������`�������ė��܂��B
���́A�����͔��䓇���w�̌i���n�A
�w�����]�x�B
���̍��䂩�痕���]�������낹��ꏊ�ɁA
�����i�����j�܂ł�����ł��B
�����@����߂� (town.hachijo.tokyo.jp)�����Ƃ���A�W���`���Ɖ��܂邱�̑����A
�ނ�łނ�������₷�ɂ͍ō��ł��I�I
�ŁA
�����]�̋��`�́A
�����A�W��
�^�J�x�A
�G�[�X��A
�T�T���E�E�E
���̑��̉�V�����_����A
�ނ�̃X�|�b�g�ł�����܂��B
�����āA����
�w�����]�x�́A
���䓇�ɍs���������Ȃ��l���A
�u�A���A�ǂ����Ō��������邩���I�H�v
���āA�K���A���������锤�ł��B
��������̔��B
���́A�L���Ȗ^�f���Ђŕ��f����f��́A
�`���ɕK���o�ꂷ��ꏊ������ł��B
�����Ƃ��A�X�N���[���Ō�����i�́A
�r�ꂽ�C�Ȃ�ł����ǂ�

�ł����A�Ƃ��Ă��Y��ȏꏊ�ł��̂ŁA
�ނ�����A�K���|�����Ă��A�艺�����ˁB
�w���m���x�Ɖ]���Ŕ̕t�����M�����A
�C�Ɍ������ċȂ�������ɁA
���̂R�̉��A�Ȃ��Ă��܂��B
���̐M���̘e�ɁA���䖼���ɂ��Ȃ����A
�w�������\�t�g�x�́A
�{�ƃ\�t�g�N���[����������܂����B
���A���N�O�A�o�c�҂̏������S���Ȃ��Ă��܂������ŁA
�ɂ��܂�X���܂����B
���₠�A�z���g�����b�ɂȂ�����ł���ˁ`
�X��̃x���`�ɍ��|���ĐH�ׂ�
�w�������\�t�g�x���b�`������������ł���B
���āA������J���A
�f�G�ȉ���ƁA
�ނ肪�Z�b�g�Ŗ��킦��ꏊ���Љ�܂��B
�u���g�i�����悵�j�v�n��ɂ���A
���֑�i�ڂ�킴��j���`�̘e�ɁA
���ǂ̋��t�����݂����Ȍ���������܂��B
���������A�m��l���m�閳���œ���鉷��ł��B
������オ�������t�����A
�f���苙����߂������t���A
�����ɐZ�����āA�b���g�̂��x�߂ĉ��߂�A
�����{�݂Ȃ�ł��B
���A���ɗD�����܂Ƃ����悤�ŁA
�O�L�����A�ǂ̉���Ƃ��Ⴂ�܂��B
�����k�����Ƃ��������ŁA
����
���ׂ������i�����čb�B�فj�Ȃ�܂���B
���₠�A�������S�O���キ�炢�Ȃ̂ŁA
�����Ɠ����Ă����銴���E�E�E�B
�ł��A�����V�����v�[�͎g���܂���B
���֑� (town.hachijo.tokyo.jp)�Ƃ���ŁA���֑`����s���ɖ߂铹������A
���䓇�ōł����P�[�V�������ǂ��A
���̖���
�w�݂͂炵�̓��x���A����܂��B
�Ȃ�Ɖ]���Ă��A�����͘I�V���C����̒��]���A
�����I�I�@
�`���[�����I�I���D�͔��䓇�̌`�����Ă��܂��B
���R�A�j��������ċ���܂����A
����i�̗����́A����ւ����ł��B
�Ȃ̂ŁA���̉^������킯�ł����A
�ǂ�����������i�Ȃ̂ŁA
�]���Ȃ���A�����ƋC�t���܂���
�ŁA��ɂ�����Ⴄ�̂��A
�����͂ǂ���������Ȃ��ł����A
�I�V���C�̃^�^�L�ŁA�܂��ςŐm�������\
�ł�

�����āA���̊J���������A�ō��Ȃ�ł�����
 ���䓇 �݂͂炵�̓��B���䓇�̐�i�I�V���C�ł��B�y�A�N���X�z (hatijo.com)
���䓇 �݂͂炵�̓��B���䓇�̐�i�I�V���C�ł��B�y�A�N���X�z (hatijo.com)���āA����
���֑`�́A
�s������͌����Ȃ��̂ŁA�ό��̐l�͗]�茩�܂���B
�ނ�l�́A�قڒn���̕��ł��B
����]�ŁA�`���͔g���Ȃ��ĉ��₩�Ȃ̂ł����A
���ʂ����ǂ��̂ŁA
�J���p�`��
�q���}�T�̃f�J���̂��A
���\�A����Ă��肷���ł��B
���ɊO��������ƍr�ꂽ��_���ڂŁA
�����A�W�̉j�����ő啨�_����������A
�������A
�����A�W�A
�^�J�x�A
�g�r�E�I�Ȃǂ̉�V�����ނ�܂��B
�������b�����ƁA
�����A�W���A���A�W�̋��e���Z���炵�����āA
�����ނ�ł�����ĕ����Ă܂�

�ȏオ�A�ނ�Ɖ�����Z�b�g�Ŋy���߂�ꏊ�ł����A
���A��ōs�������́A
�悸����������Ȃ��ł��傤����A
�ނ�ƁA������Ċy���ގ������܂��B
�ނ�̃|�C���g�ł���A
��h�ނ�Ȃ�A
�_�����`�E
��y���`�E
���d���`�E�E�E
���݂�
��y�`���A���C�D�D�̑D�������`���邽�߁A
�����ނ�֎~�ł��B
��ނ�̃|�C���g�́A
�s�������̍~����̏��ɋ��}�[�N�̊Ŕ������āA
��������n��ɏo���܂��B
�i�Y�}�h�Ƃ��A
�N�j�m�~�`�A
�A���C�P�Ȃǂ���܂��B
����́A�~����
�u�ӂꂠ���̓��v���A�I�X�X���ł��B
�R���i����������A�������y����ʼn������B
�D��

�A��s�@��

�A�A�N�Z�X���܂���[�I�I
�������A���N�����͔���ɋA��܁[��