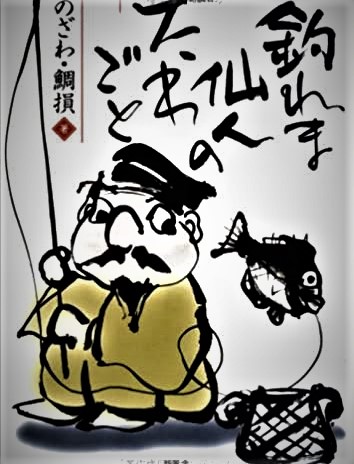�����������ł����A
�R���������āA�����ɍs���ɂ��N���}�Ȃ̂ŁA
�����ł���A���Ɂu�����Ȃ��E�E�E�v�Ȃ�āA
�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����H
�ł��A�R�������āA�������v���ȏ�ɍL���ł����A
�������R���[���\�B�̂ŁA�������ɗ���Ă��Ȃ���A
���̐�ɂ���āA
�����ɐ������鋛�ނ̐��������A
����Ă�����������ł��B
�ł����ꂱ�����R���̌k���̓����ł���A
���͂Ȃ̂�������܂���B
�Ⴆ�A������Љ���đՂ����A
�������𗬂��A�R�������������NJ�����͐�ƁA
�����E���k�������NJ�����͐�́A���ɕx�m��̉͐�ł��B
�x�m��Œނ��k�����Ƃ��đ����̂́u�A�}�S�v�ł����A
�������Љ�錧�����𗬂��͐�́A
������A���͐�ł���A������Œނ��̂́A
�A�}�S�ɗǂ����Ă��܂����A�u���}���v�ł��B
�����ڂ́A�g�̂̑��ʂɎ�_�����ł邩�ǂ����E�E�E�B
�ƁA�p�b�ƌ��ł́A�قڕς�Ȃ��̂ŁA
���݈�ł���R�����ł́A�ǂ������ނ�Ă��A
�u���}�����I�I�v�ƁA�f�����ď���Ȃ����������ł���˂�(*^_^*)
������ƌ����āA�ڂ�����𗧂Ă�K�v�͂���܂��A
�ł��A�͐�ɂƂ��Ă͊��ƃV�r�A�ȏɂȂ�܂��̂ŁA
�x�m��Œނ����A�}�S���A�u���}��������E�E�E�v�ƁA
������̉͐�ɕ�������悤�Ȏ��́A
��ɂ��Ȃ��ʼn������ˁB
�Ƃ���ŁA����Ɠ��l��
�����͐�̉��֏����A
�R�������Ƌ����g���A�����HP�ŁA�m�F���ĉ������B2021�N �k������������ ���֓��y�ї��� - �R�������Ƌ����g���A����b�R�����b�ނ� (yamanashi-gyoren.com)�܂��A
�V���K���Ƌ���̊m�F�ɂ��ẮA
�R������HP�Ŋm�F���ĉ������B
�R�����^���Ƌ����g�����Ƃ̗V���K���Ƌ���} (pref.yamanashi.jp)���̂����ŁA���̓��e�ł́A
�������̋��������HP�Ƀ����N��\��܂����B
�Ȃ̂ŁA�ލs���v�悳��Ă�����́A
���ځA���d�b���Ŋe�����ɁA�ڍׂ�q�˂ĉ������ˁB
�ł́A�R���������̋�������́A�ȉ��̃����N����E�E�E
1�A�@�j�싙���j�싙�Ƌ����g�� (katsuragawa-gyokyo.net)2�C�@�s�������i�j�쉺����j�s�����Ƌ����g���@�����T�C�g – �����̂��߂Ɏ��R�ی슈������@Tsuru Fisheries Cooperative (tsuru-gyokyo.org)1�E2�͂�������A���Ɏ�s���̃t�@���������ł���ˁB�����ߔN�A��C�Ƀ��A�[�E�t���C�̒ނ�l���A
�������悤�Ɋ����܂��B
3�A�����������i�A�����֓���3��6���̗\��j���������� KOSUGE River | ��������ނ����֓��ŏ��߂ă��A�[�E�t���C��p���݂��A
�L���b�`�������[�X��Ԃ��ݒ肳��܂����B
4�A�O�g�R�����@����HP�����B�i�A�����ւ�3��15���̗\��j
3�E4�́A�����������̉����~�\�B������̌����ł��B
�ŋ߂́A�O�b�ƃA�N�Z�X�����₷���Ȃ��Ă��܂��B
5�A���u������
�������Ƃ��Ă̌���HP�͂���܂��A�ȉ��Ŋm�F���ĉ������B���u�����Ƌ����g���b���u��k���t�B�b�V���O�Z���^�[ (goope.jp)6�A�H�R�����@����HP�����B
5�E6�́A���l�Ȃǂ̐����߂ɂȂ��Ă��鐴���ł��B
�܂��A�����ׂ����͐쐅�n�̏ڍׂ́A
���͐싙�A��HP�������������B���͐싙�Ƌ����g���A���� (sagamigawa-gyoren.jp)�ȏオ�������̉��֓��̏��ł��B
���A
�ނ�́u�s�v�s�}�̊O�o�\�v�ł́A����܂���B�ލs�ɂ��ẮA�n�l�̂��������߉������B
�܂��A���ً̋}���Ԑ錾�̉����ɂ��ύX�ɂ��Ă��A
����̋�������ɕK���₢���킹�Ă���A
�ލs����悤�ɂ��ĉ������ˁI�I
��̎ʐ^�́A�����u���u��v�ł��B
�{���ɐ��炩�ȗ����X���Ă��܂��B