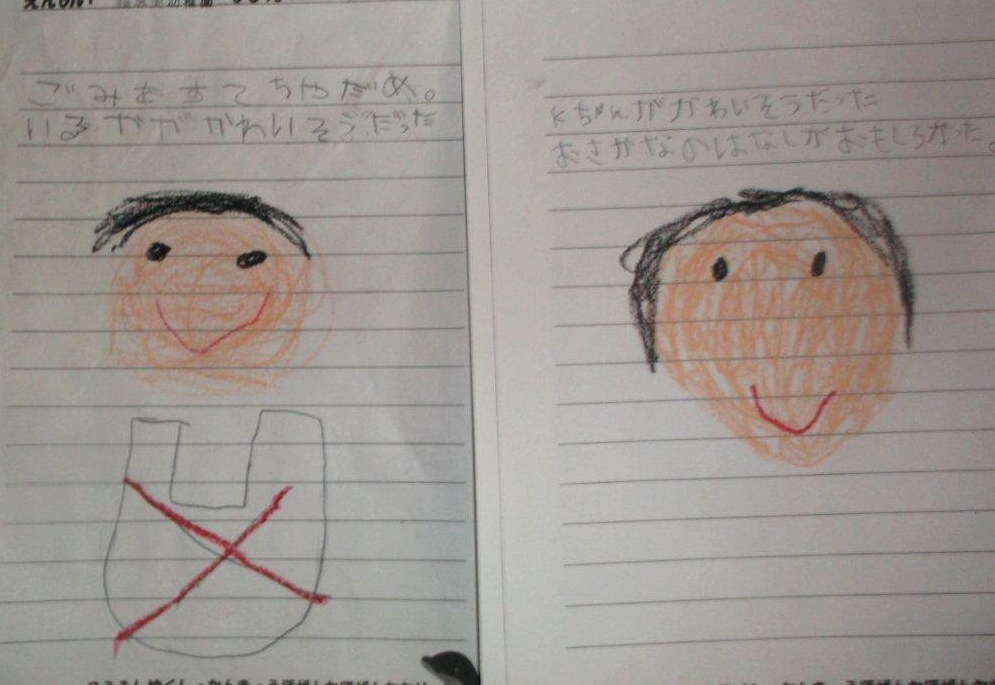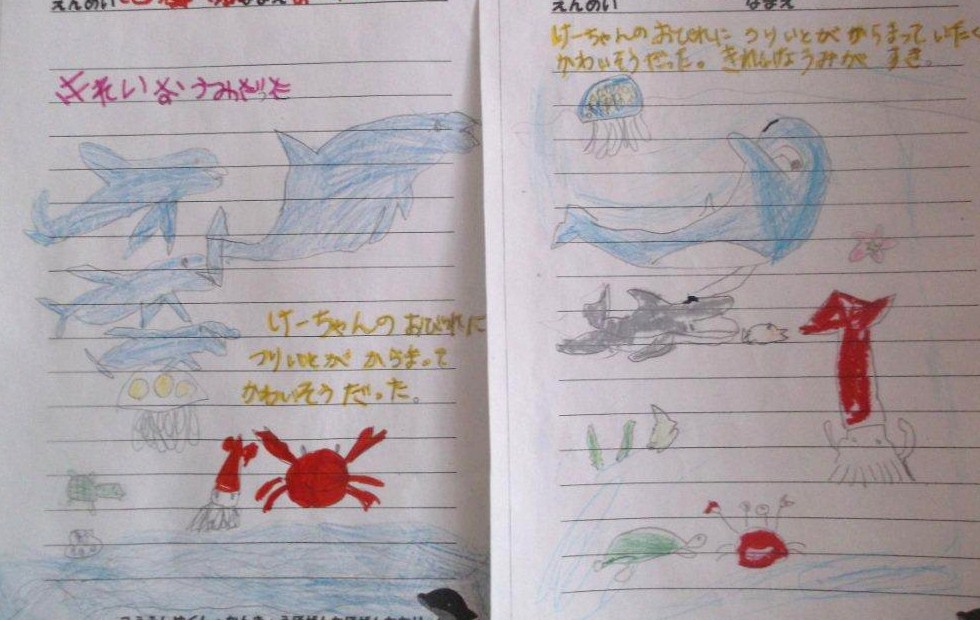今年も激動の日々だった8月。
しかも、猛暑で台風ラッシュの8月でした。
身体の疲れは、まだ癒えてはいませんが、
既に9月が始まってしまいました。
さて、だいぶ遅くなってしまいましたが、
今日から今年の海洋道中の、
現地研修のレポートを始めていきたいと思います。
が、お詫びをしなければならない事がございます。
それは、八丈島に着いてから、
いきなり自分の持参したデジカメが、
使用不能になってしまいました。
依って、このブログでも、
今年の海洋道中のレポートが、
文章のみになってしまいます事を、
どうかお許し下さいませ。
まずは、子供達が島に着く前の、
先発隊での2日間を振り返りますね。
7月30日。
2便に搭乗した、先発隊の3人組。
離陸までは順調でしたが、
なんと、島の上にかぶさった積乱雲―。
気流が乱れて、なかなか着陸ができず、
島の上を旋回し続け、
3度目のチャレンジで、ようやく着陸( ;∀;)
下手すれば、引き返す事もあるだけに、
ヒヤヒヤものの着陸でありました。
台風12号の影響で、
ひょっとすると、荷物が着いていない―
って事も予想されたのですが、
ホント間一髪で間に合って、
早速、ベースキャンプの準備に取り掛かりました。
でも、飛行機が遅れたこともあって、
初日に建てたテントは5張だけ。
夜は、スコールが断続的にやって来て、
ウトウトしたと思ったら、ザーッ・・・
何とも寝苦しい夜を過ごしましたとさ。
この日のトピック。
晩ご飯を、ご馳走になったのですが、
締めに・・・と、勧められたのは、
島とうチャーハン!!
島唐辛子の辛さは、もう十分わかっているので、
とりあえず、3人で一人前を食す事に・・・
「いっただきまーす」香りもチャーハン
「ウン、ウマ・・・( *´艸`)」
「か、辛い・・・」
3人の男どもで、涙と汗をダラダラ流して、
やっと一人前を食べ終えました。
やっぱり、なめたらあかんぜよ( ;∀;)
さあ、明日もベースキャンプの準備、
頑張りましょうね〜!! |