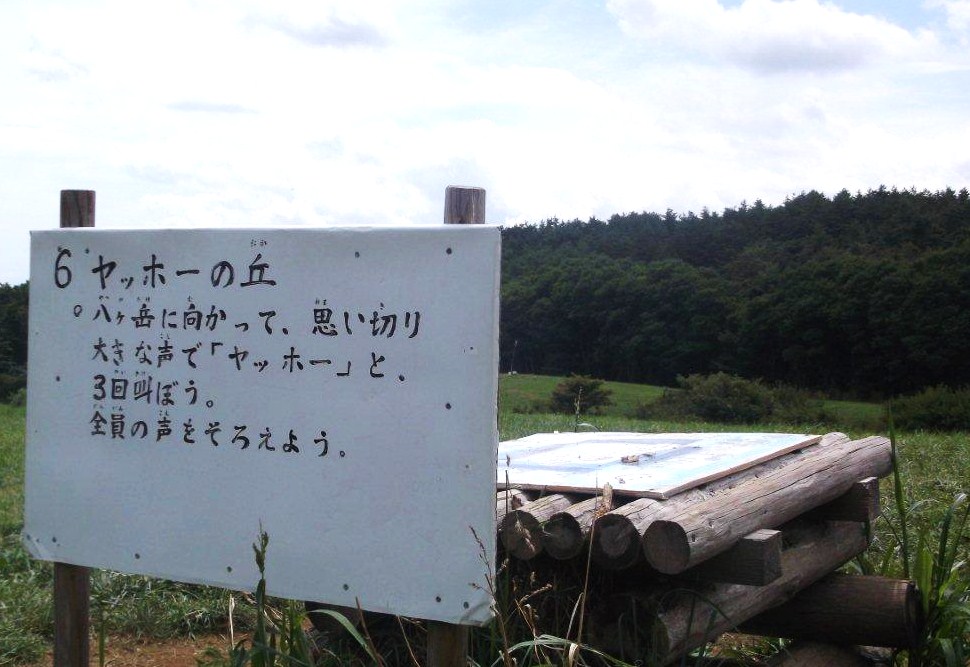実習の3日目(5月25日)からは、
実習のステージは、海辺に繰り出す事になります。
その最初の活動として、
例年「海釣り体験」を、行っていますが、
今年から、これまでの糸魚川方面ではなく、
柏崎へと会場を移す事にしました。
海釣りのはじめの一歩として、
堤防での釣りは、安全だし、格好の場所―。
と、思われている方が殆どかと思います。
が、実は、堤防と云うのは、
釣りではない、本来の目的があるので、
勝手に釣りができる―。と、云う場所ではありません。
港湾局や、漁業者により、
管理されている施設ですから、
釣り人は、本来なら入ってはならない場所なのです。
が、現状では、ほぼ「黙認」と、云う形で、
釣り場として、少し借して戴いている―。
と、云う事になるのです。
なのに、心無い釣り人が、
「釣れるから・・・」と、無断で入りこみ、
海難事故に遭ったり、
漁業者とトラブルになったりと、
そんな事が多々あり、
結果、行政と好ましくない状況になり、
釣り人が自らの首を絞めてしまって、
釣り場を追われているケースが、
実は、全国にはたくさんあります。
今回、釣りを行った柏崎の堤防も、
釣り禁止でありながら、不法な侵入により、
何件かの死亡事故も発生していた堤防なのです。
が、禁止にするから、不法侵入する―。
と、云う負のスパイラルを断ち切る為に、
しっかりと管理して、
ルールを徹底して守らせる事で、
釣り場として「解放」して戴く―。
その様な釣り場が、この新潟県をきっかけにして、
広がりつつあります。
そして、地元の釣り業界の有志を母体とした、
NPO法人を立ち上げ、
ここを管理する事になったのです。
そのNPOこそが、ハッピーフィッシングです。
釣果の実績もあり、
こうした釣りの、好ましい在り方を考える上でも、
今年からは、是非ここを活用しよう!!
と、云う事になったのです。
以前にも紹介致しましたが、
この実習の目的として、海の恵みは自ら確保し、
それを「食す」と、云う、
プチサバイバルな実習なので、釣れないと、
食事のおかずが無い訳で、必死にならざるをえません。
が、がっ、
前日までの釣果は、好調だった様なのですが、
この日は朝から・・・。
と、受付のスタッフさんから、
「苦戦」の宣告を受けてしまってからの、
実釣となってしまいました。
スタッフさんの予見はバッチリ当たってしまい、
釣れるのは、クサフグばかりで、
食材とできるお魚さんが、
なかなか釣れてくれません(涙)
で、ここで頑張ってくれたのが、
保育士を目指す2名の女子学生です。
苦戦する男どもをよそに、
見事に「食べられる魚」を、ゲットしてくれました!!
やっぱり、頼れるのは、
今や女子なのかなあ・・・。
で、こんな釣果がありました。
写真は、
1枚目 カナガシラをゲット!!(2尾釣れました)
2枚目 こちらは、メバルをゲットです。
ちなみに、何故か投げ釣りで、
美味しいバイ貝を2点がけしたり、
食べられる海の恵みをゲットしたのは、女子のみ!!
ありがとうございました・・・
お陰でなんとか晩ごはんは、
ブイヤベース風のスープを作って、
みんなで味わうことができましたとさ!!
感謝!!
|