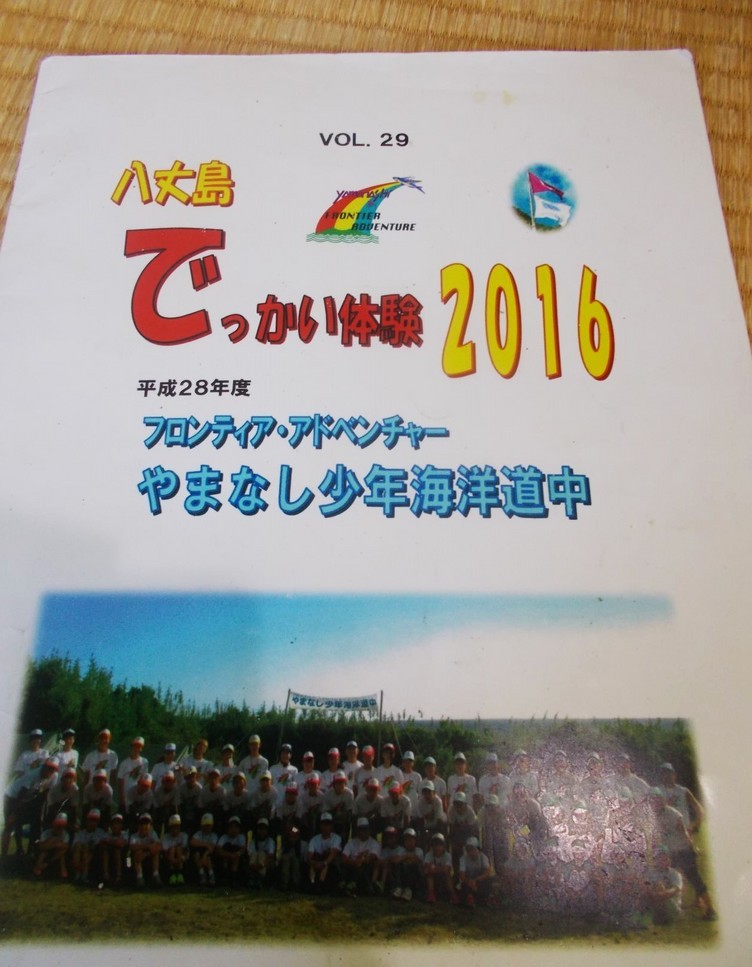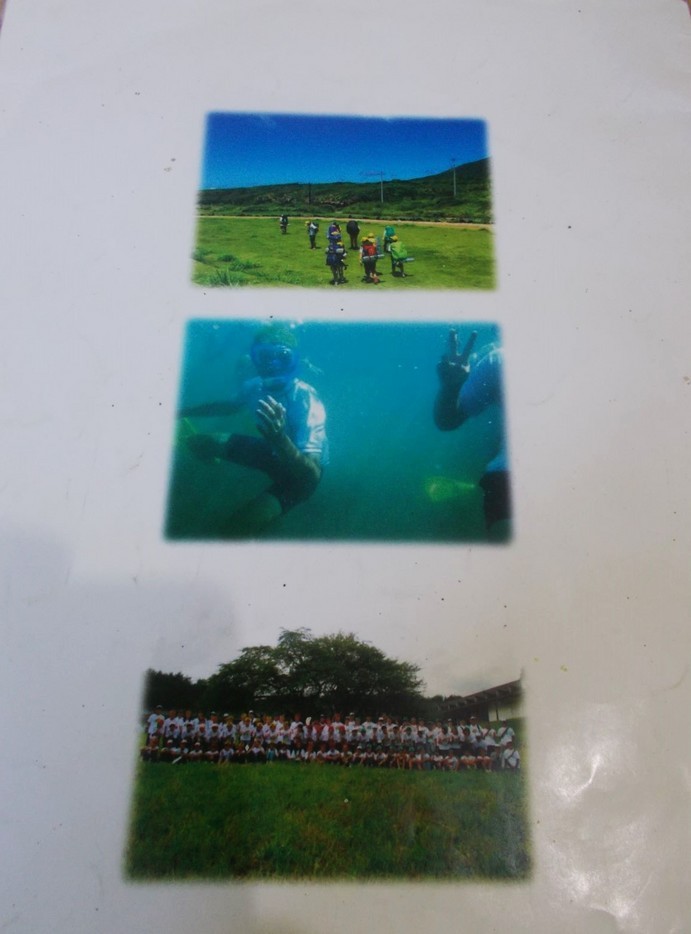皆様おはようございます。
今日は、お盆休みの最終日ですが、
3年ぶりの行動制限がない夏―
皆様は、何処かに行かれたでしょうか。
さて、
出発直前で県内でも1000人を超える感染者が相次ぎ、
ギリギリまで実施が危ぶまれた、
今年の『やまなし少年海洋道中』が、
8月1日〜8月8日までの7泊8日―
八丈島で、無事に実施されて、
8日の深夜に、山梨に戻って参りました。
期間中、ただの一人も感染者を出す事なく、
最後まで活動出来た事は、
ある意味、奇跡の様なキャンプでした。
3年ぶりの開催は、
思うように行かないことも正直ありましたが、
何より実施出来た事―
それだけでも、大きな大きな意味ある海洋道中でした。
そこで今日から、
先発隊として7月31日に八丈島に入った日から、
8月8日に、山梨に戻って来るまでの日々を、
順を追って紹介させて戴きます。
コロナ禍でのプログラムは、
例年とは並びも、日数も違いますが、
子ども達は、でっかい体験の数々を、
存分に味わう事ができたと思っています。
今日は、八丈に到着していきなり食らった、
灼熱の暑さの中での、
先発隊3名の奮闘ぶりを書きたいと思います。
暫し、お付き合い下さい。
羽田からのフライト時間は、
たったの40分ほど・・・。
10時間半ほど掛かる船旅とは、
感じる距離感は全く異なるのです。
が、着いて早々、
ジリジリ肌を焦がす様な、
強烈な日差しが

照りつけていました。
地元の方でさえ、
こんなに暑い夏の八丈は初めてだと・・・
日焼けには充分に注意するようにと、
アドバイス戴くほどだったのです。
先発隊の役割は、
ベースキャンプの一部設営と、
お世話になる方々、そして施設へのご挨拶回り。
そして、ある程度の島の環境の把握です。
着いたのが午後2時頃でしたから、
こんな暑さの中で、
いきなりテントアップなどすれば、
たちまち熱中症でダウン―
そんな光景が脳裏によぎり、
危険を感じた我々は、
先ずは島内把握から開始する事にしました。
自分がナビゲーターとして助手席に座り、
先ずは、BC周辺と空港周辺の道路を、
把握する事からスタートしました。
最初に訪れたのは、底土港―
8月2日になれば、
ここに橘丸が着岸して、
子ども達が初めて八丈島に上陸します。
隣接する底土漁港では、
日曜日という事もあって、
「浜遊び」を、楽しんでいらっしゃる姿も、
目に飛び込んで来たのでした。
続いて向かったのは、
南原エリア―
宇喜多秀家と、豪姫が都を思い太平洋を眺める、
銅像と、その絶景を見てもらいました。
南原から見えた景色は、
これまで以上に新鮮で美しく、
「帰って来たぞ!!」と、
思わず叫んでしまいそうな程―。
その後、八丈高校を確認し、
八重根港・八重根漁港をチェックして、
期間中お世話になる島のスーパーを視察。
そして、午後4時過ぎに、
やっとBCを張る垂戸に戻りました。
それでも、まだ暑さは収まらず、
暫し休憩をして、ようやく作業が始まったのは、
午後5時頃。
ここから、
先ずは我々が今夜眠る3棟のテント張り―
ですが、ここでもブランクはいかんともし難く、
3棟張り終えるのに2時間も掛かり、
お風呂にも行けず、真っ暗になってしまいました。
そこから、上陸最初の夕食―
の、筈だったのですが、
やっているお店がほとんどなーい

で、夜道をレンタカーでうろうろ。
しーすーもダメ

お魚料理のお店もダメ

で、やっと見つけたのは、
おおよそ教育キャンプには相応しくない、
凄いインパクトのある四字熟語のラーメン屋さん。
でしたが、
これが、予想を裏切る美味しさで、
大盛りのつけそばを全員完食。
とんこつ醤油のスープは絶品です

もっと驚いたのは、オーナーさんが、
イケメンの外国人さん、即ちYOUでして、
いやあ、美味しかったです。
お風呂

に行けなかった我々は、
近くの海水浴場のシャワーで水浴び。
その後、山梨では到底見られない、
見事な星空

を見上げながら、
おっさん3人で、語り合いあったのでした。
明日は、本部のテントを建てたり、
水場や、照明なども整備しないといけません。
流れ星

に手を合せ、
明日からの無事を祈った先発隊でした。