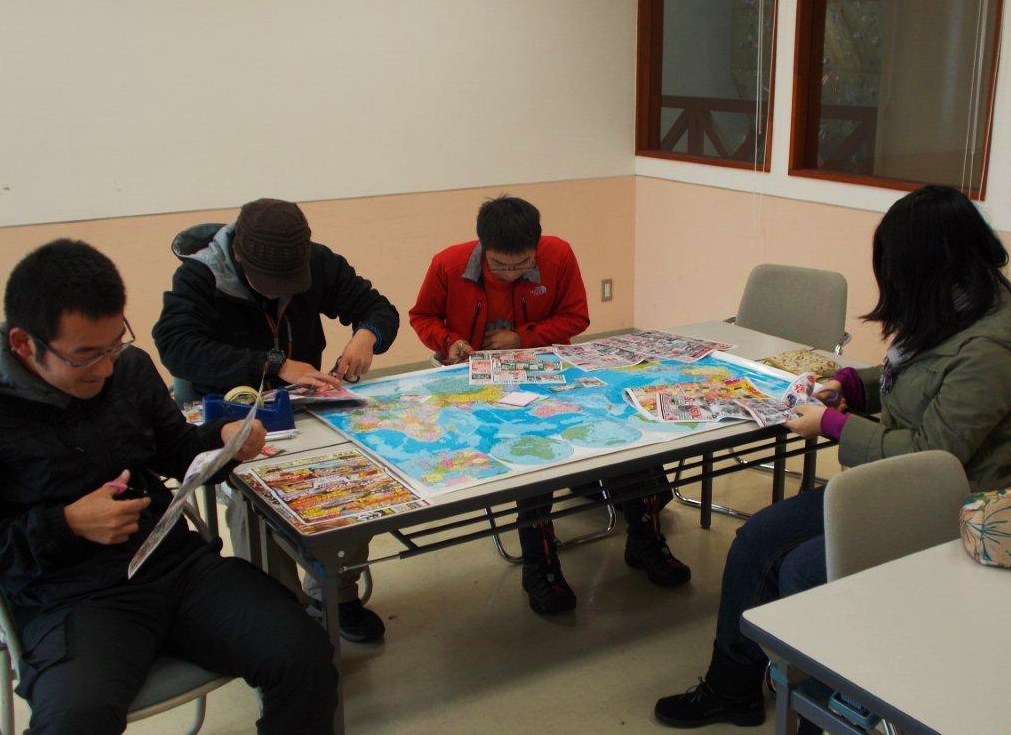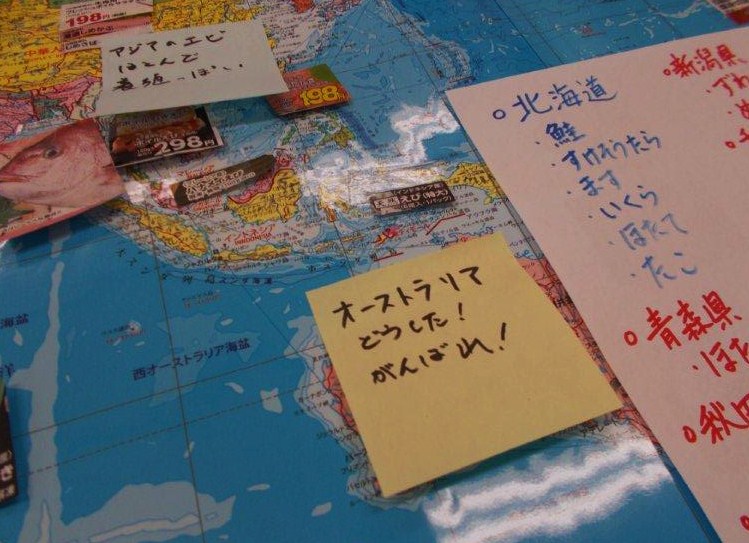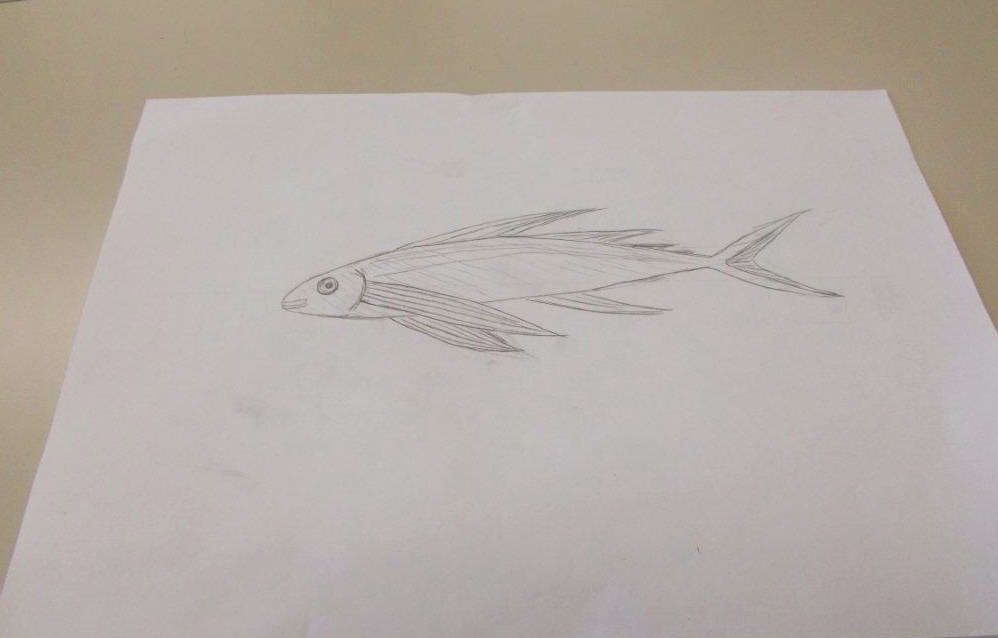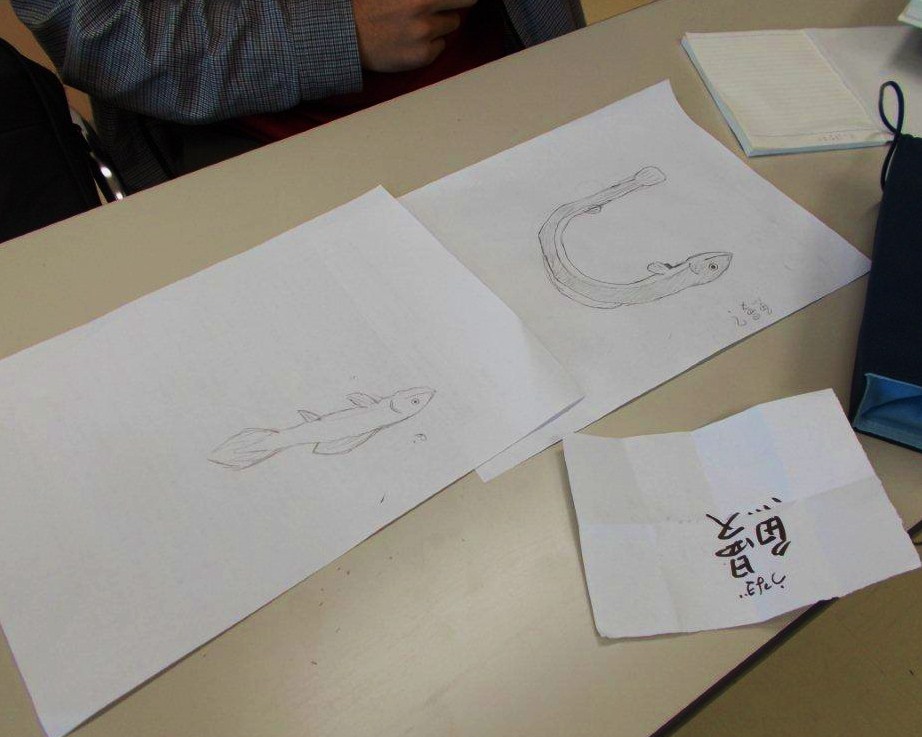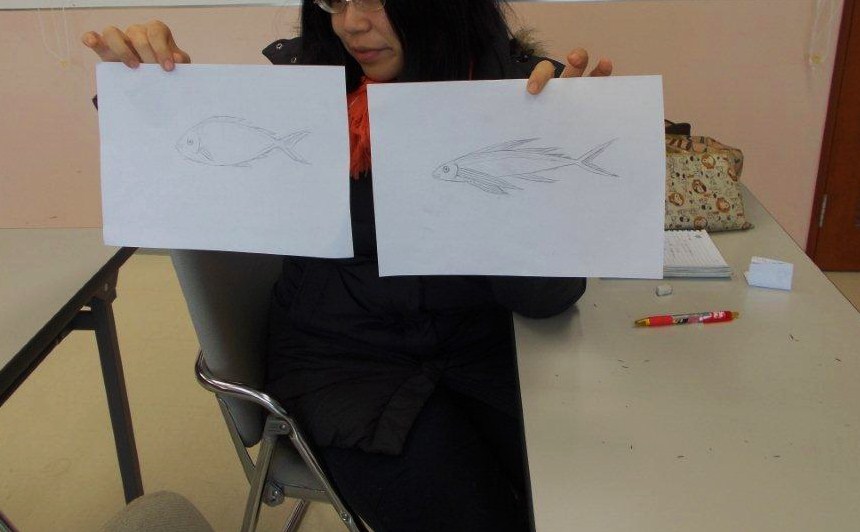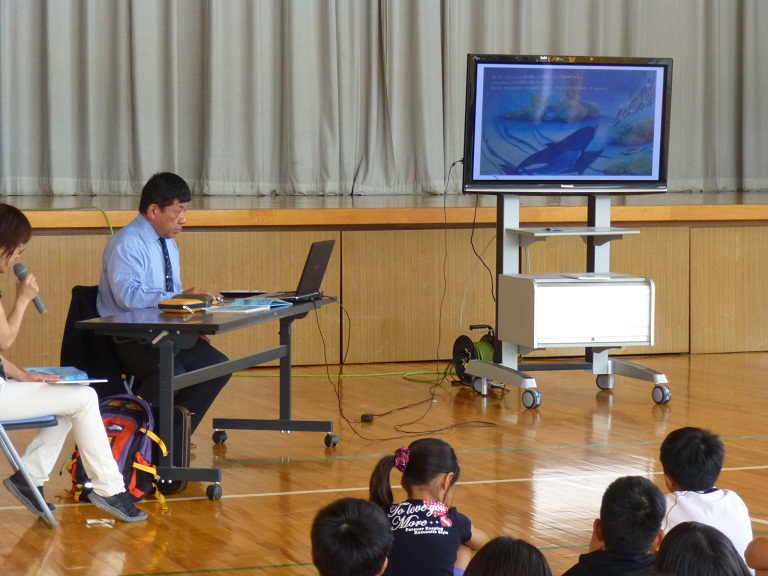日本の食文化として『和食』が、
ユネスコの世界無形文化遺産に登録されました。
食の中に、四季と、美を取り込み、
日本独自の世界観で、発展して来た料理です。
実に嬉しいニュースでしたね。
さて、そんな和食の中でも、
「魚食」の、文化は、特に素晴らしいと言えます。
周囲を全て海に囲まれた島国だからこその、
魚食を、後世にも、ずっと伝えていきたいですね。
そんなホットなニュースと絡めて、
11月28日の、水辺の環境教育学の授業では、
エコフィッシングの第二弾として、
釣ったつもりで、魚料理にチャレンジしました。
学生達が選んだ旬の魚は、鰤(ブリ)
初めてのチャレンジとしたら、
かなりなハードルの高さではありますが、
難しいからこそ、
もてなす気持ちは、強くなると云うもの・・・。
大型の魚体を捌きながら、
魚の体のつくりを知り、魚の全てを活かしきる、
そんな料理を考えました。
メニューは、
鰤のお造り
あら汁
カマとカブトの塩焼き
そして、もう一品は、
私が、鰤のカツレツを作ることになりました。
三枚下ろし一つにしても、悪戦苦闘です。
ウロコを梳き取り、
中骨に沿って、身を半身づつ切り分け、
さらに割くに取ります。
見ていると、ついつい口も手も出てしまうので、
私は、背中を向けて、カツレツに集中です。
かなり時間はかかってしまいましたが、
自家製の味噌を加えての「あら汁」も、
丁寧にアクを取りながら仕上げていきます。
カマとカブトの塩焼きも、
遠火の強火で、ていねいに焼き上げていきました。
最後に、強火で表面を、美味しそうに炙りました。
鰤のカツレツは、
ネギマの串カツにしました。
IHクッキングヒーターを使って、
ゲストの目の前で、
揚げたてを味わってもらう事にしました。
放課後のロビーには、
授業を終えた学生たちや、先生方、OBまでやって来て、
旬の鰤を、存分に味わってもらいました。
味も、とても評判でしたよ v(^v^)
命を戴いて、自分の命を繋ぐ「いただきます」
食材を得る為に、馳せ走り、
美味しく食べてもらうために料理する―。
そんな気持ちに感謝する「ご馳走さま」
もてなし、もてなされる、喜びを感じた授業でした。
ホント美味しかったよ!!
お疲れ様でした。
写真は上から
1枚目 さあ、鰤は手ごわいゾ!!
2枚目 それぞれの料理に合せて切り分けています
3枚目 あら汁のアクは丁寧に取り除きます
4枚目 タダ飯屋のテーブルには鰤尽くしが並びました
|