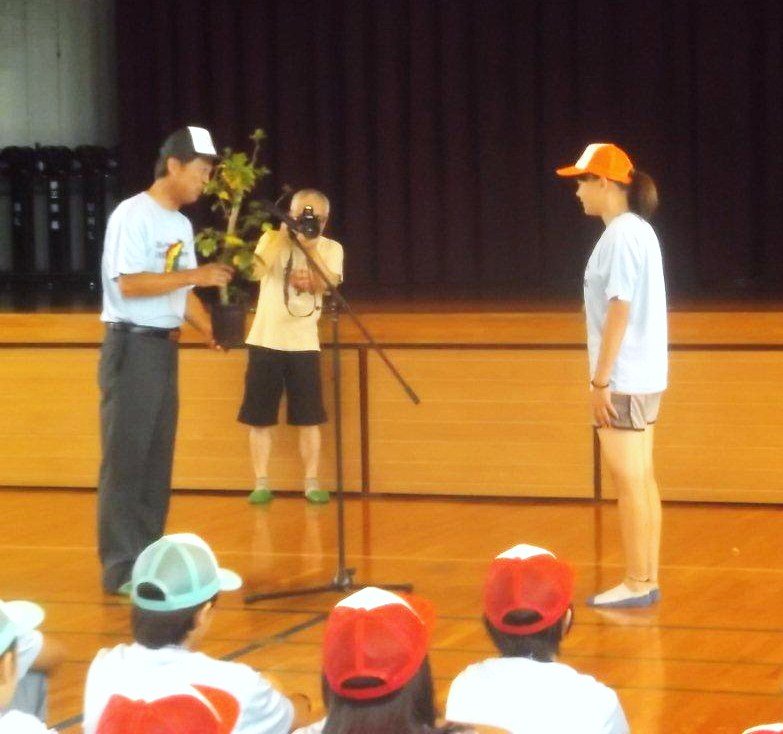8��4���́A�u�C�m�̓��v�ŁA
����̊C���A�܂邲�Ɛg�̂ő̊��ł���A
�X�y�V�����ȓ��ł��B
���A���͂��̓����A�`���C�ƊC�͍r��͗l(>_<)
�䕗�T������̉������˂肪�����āA
�J���p���p���E�E�E�B
���D�ɏ���ẴN���[�W���O�͔����ł����B
���A�u�����������Ă���Ă���̂�����E�E�E�v
���D�̑D������B�̐��Ȍv�炢�ŁA
�Ȃ�Ƃ��N���[�W���O�D���o���Ă���邱�ƂɁ\�B
���т̎q���B�ł͂���܂������A
�ŏ��̐����͂ǂ��ւ��E�E�E
�O�C�ɏo�āA�D���h��n�߂�ƁA
�e�ǂɂ���āA�����Ԍ��C�ɍ����o�n�߂܂����B
�����B�D�����ł�(>_<)
�␅�����Ă���Ƃ̏��������āA
�����̓o�[�b�Ɣ�яo���g�r�E�I�������A
�傫�ȃE�~�K�����A�p�͖w�nj����܂���ł����B
�ł��A���䓇�̓`���̋��ł���A
�����A�W�̖_��ԋ����ԋ߂Ɍ����Ă���܂����B
�ŁA���̎��A�����A�W�̑��ɁA
�J���p�`���Ԃɓ������Ɖ]�����ŁA
4���̂Q�`�قǂ�����J���p�`��Ղ��܂����i�O���O�j/
���̃J���p�`�́A�[���Ɏ������J���āA
�q���B�Ǝw���҂Ŕ��������Ղ��܂�����`�I�I
���܂��������I�I�I
���āA�C�m�̓��́A�����̒ʂ�A
���̎Y�Ƃł���A�u������v�́A
�H��̌��w�������đՂ��Ă��āA
���N���A�����A�W���J�����đՂ�����A
�Ă����Ă̂���������H�����đՂ�����A
�ŏ��͓Ɠ��ȍ�����S�O���Ȃ�����A
�H�ׂĂ݂�ƁA�u�E�}�C�v�ƁA�Ȃ��āA
���N�����ǁA��D�]�̎��H��ɂȂ�܂����B
�H�ו��̐l�C�́A
���N�̓N���[���`�[�Y�����ĐH�ׂ�\
���A�l�C���������ȁi�j
������̗��j��A���̍����ȂǁA�w�т܂����B
�������͂���A���ؔ���o�[�W�����ł��I�I
�����̂��ꂳ�����A����ĉ��������A
���̗����ɐ�ۂł��B
���̎q���B�ɑ�D�]�́u�����A�W�o�[�K�[�v���A
������N���_���g�c�l�C�ł�����B
�����������܂ł����B
�ߌ�́A����ł��Ȃ������X�m�[�P�����O�����s�I�I
���N�́A����̊C��~�����̕��X�ƁA
����ψ���̃X�^�b�t�̒����猵�I���ꂽ�A
���s�X�^�b�t����̃��[�h�Ŏ��{�Ƃ��܂����B
���̕������X�N���y���ł��邵�A
�����t�B�[���h���n�m����Ă�����X�����ł�����A
�f���炵���C�̒����A�q���B�Ɍ����Ă����ƁA
���f��������ł��B
�����ȏ�ɁA�ϋɓI�ɉj���ŁA
�����������āA���������q���B�ł����B
���܂��́A�߂��Ă���̃J���p�`���H��i�O���O�j
�}�C������čs���Ă悩�������I�I
�ʐ^�͏ォ��
�P���ځ@
�ŏ����w��ɏW�܂��Ă͂��Ⴂ�ł��܂������E�E�E
�Q����
�D���~�肽��ł̃X�i�b�v�B�`���b�Ɗ�F�����ˁI�H
�R����
������E�}�C�I�I
�S����
���̎J�����̑̌��ł��B�Ȃ��Ȃ����ł�����I�I
|